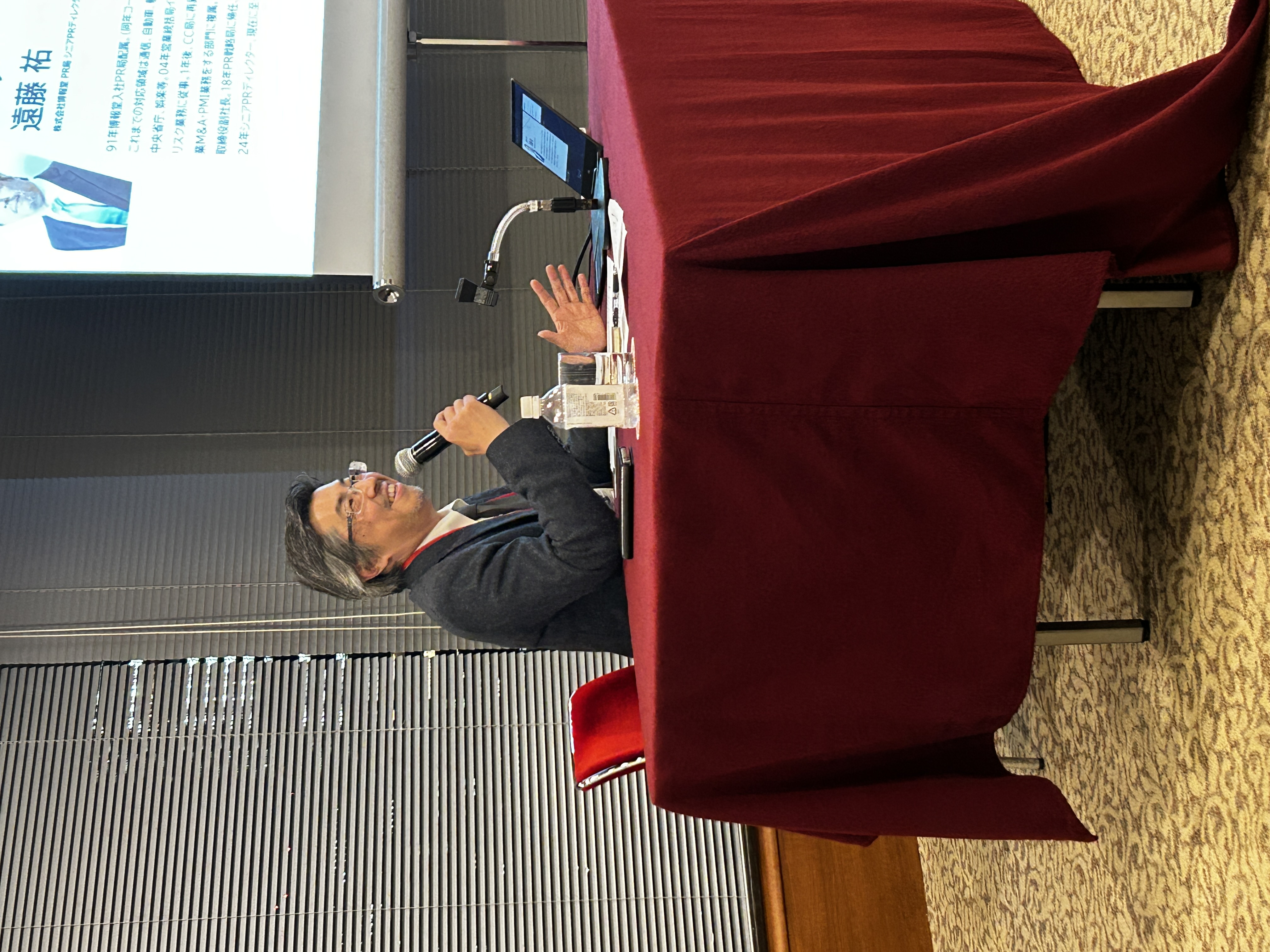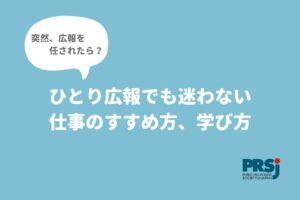「広報部長スキルアップ講座2024」は、各業界の広報に関わるマネージャークラスの方を講師に迎え、広報部門のリーダーに求められるスキルやメディア対応の視点、法的リスク管理について学べる実践的な講座です。
今回は広報委員有志メンバーが当日のセミナーの模様をレポートいたします。
開催の様子
第一部 「メディアからみた企業の経営や広報」
講師:円満 亮太 氏(朝日新聞東京本社 経済部長)

第一部は、朝日新聞の円満亮太氏(東京本社 経済部長)が登壇し、メディア視点で見る企業の経営や広報についてお話しいただきました。事前に現場のキャップの方々にヒアリングして準備してくださったとのことです。
朝日新聞経済部が注目するのは、新商品・サービスに垣間みえる社会の変化とその先、また企業の「生きざま」。題材を選ぶ上ではPVにこだわり過ぎないことにも触れられました。広報に伝えたいことは (1)記事化は必ずしも約束できず、取材してみないとわからない (2)数字的な根拠がない情報やキャンペーン情報は基本的に難しいものの、例えば激しい円安といった社会性を感じさせるケースは例外もある (3) 苦労話、失敗談など、ネガティブにも捉えられる情報があると物語に起伏が生まれ、記事にしやすい――ということです。
会社や経営者に対しては、「従業員を大切にしているか」「消費者・株主などのステークホルダーとどう関わっているか」「企業活動によって社会的な価値を生み出しているか」「経営者が広報部門に権限を与えているか、広報部門が元気かどうか」といった観察のポイントを挙げられました。広報担当とメディアの向き合い方に関連して、 記者のタイプに(1)採取型(木の実や虫を探して集める)(2)狩猟型 (3)農耕型(種を撒いて時が来たら刈り取る)があるというお話しがありました。ご本人は農耕型ということですが、相手にあわせた対応を考えるヒントになりそうです。
第二部 「危機管理・企業ガバナンスと広報部長の役割」
講師:鈴木 悠介 氏(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士)

第二部では、鈴木悠介弁護士(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー)が登壇。かつてテレビ局の報道記者として企業不祥事の取材にあたっていたご経歴から、危機管理案件における顧客の広報部門とのやり取りも多く、自社の広報部のアドバイザーでもあります。このセッションでは、広報部長が意識すべき法的なポイントをはじめ、危機管理や企業ガバナンスの要諦を解説いただきました。
広報業務に関連する法的分野は、著作権、肖像権・パブリシティ権、商標法、景品表示法、個人情報保護法、イベント関連の規制(道交法、消防法など)、不正競争防止法、下請法、特定業種での広告規制(金融商品、医薬品など)と多岐にわたります。中でも著作権侵害や景品表示法違反は、摘発件数が増加しているとのことです。著作権については、フリー素材サイトから入手した画像の使用や、引用元を明記したうえでの共有も侵害事案となりうるとのこと。また景表法について、仮に消費者庁から優良誤認表示(商品やサービスが実際より著しく有利であると誤認させるような広告表現)の指摘があった際、根拠となる資料を15日以内に提出するよう求められるということです。こういった環境の中で広報部員の意識を高めるためには、近時の摘発・訴訟事例やヒヤリハットの共有、また「消費者庁や警察などから疑われること自体がレピュテーションリスクにつながる」という意識を持つことをアドバイスくださいました。
危機管理については、外部との接点を持つ広報部門こそ、企業の存在価値を自問自答し、経営・ガバナンスにフィードバックする役割を担うべきと強調されました。不祥事を起こす企業の多くには、その理念が社内で十分に共有されていないという共通点があるとのことです。通常から着手できることとしては (1)危機管理対応マニュアルの確認 (2)不祥事の公表基準策定 (3)社内のリスク感度を高めるための研修(特に模擬記者会見)を挙げられました。
第3部 パネルディスカッション 企業経営における広報部長の役割とは
講師:飾森 亜樹子 氏(三菱UFJフィナンシャル・グループ、チーフ・コーポレートブランディング・オフィサー 経営企画部部長)
講師:坂本 香織 氏(第一生命ホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーションユニット長)
講師:相川 貴之 氏(いすゞ自動車株式会社 広報部長)
モデレーター:遠藤 祐 氏(株式会社博報堂 PR局 シニアPRディレクター)
|
|
|
飾森:コミュニケーション人材の定義や育成についてはずっと考えてきましたし、今でも悩んでおります。NEC時代は自分の部門をどういう人材で構成したら組織が強くなるかと考えていました。まず自分の後継者を含むリーダー層があり、そこに色々な部門のリーダー候補を連れてきて将来につなげる広報の経験をしてもらっていました。コーポレートコミュニケーションは経営戦略の中枢にありますから、必ずよい勉強になると社内で宣伝したのです。そして、部門を強くするためには転職してくるプロ層も必要だと思っていました。また、銀行はジェネラリストが中心ですが、時代の流れでプロフェッショナル制度ができ、コミュニケーションの専門職を設けました。スキルや経験、どうあるべきかなどを定義し、その中にはPRプランナー資格も要件にいれています。
坂本:担当者に身につけて欲しいスキルは一覧にしています。中でも、異動してきた方に必ずお願いするのは経営リテラシーです。経営戦略やコーポレートガバナンスをきちんと理解する。さらにはESG、IR、法務観点なども含まれます。大変ですが、知っていることで広報活動のクオリティがあがることをご理解いただきたいと考えています。私自身「困ったら勉強する」スタイルが好きなので、メンバーにも積極的に外部で勉強していただき、それをアウトプットしてもらうことを意識しています。また、全員が同じことを得意でなくてよいとも思っています。特定の事業や人事など、得意分野で輝けるようにフォーメーションを組みつつ、新たにインプットする部分とバランスよく成長していただければと考えています。
相川:世の流れで人事制度がジョブ型に変わってきましたので、「この領域~年やっていました」では通用しなくなってきました。PRプランナーなどもひとつですが、自分ができることをどう端的かつ説得力を持って示せるのか考えよう、とメンバーを促しています。転職組が多く様々な特技を持つ人材が集まっていますが、たとえばSNSの運用に長けているものの、適時開示のポイントをまったく知らない、といったケースもあります。得意なところは伸ばしながら、コーポレートコミュニケーションとして抑えるべき領域はどこかである程度経験をしてもらう、そういう道筋をつくっていけたらなと。比較的若い方々には、組織として意識的に機会を作ってあげるほうがよいかなと考えています。
現代における広報業務とは
飾森:私は「会社を変革するコミュニケーション」と「社会をよくするコミュニケーション」を仕事のモットーとしています。前者について、現職では二つの仕組みを作りました。一つ目「カルチャー改革のフレームワーク」は、働く環境、社員のマインドセット、実践する機会の3つに沿って、行動パターンの変革に向けたものです。経営企画部、人事部など関係部門で施策を打ち、効果を調査し、次の年の施策につなげるというPDCAです。目標のために全社で取り組む仕組みをつくり、実施していく。これも統合的なコミュニケーションのひとつだと思っています。もう一つはパーパスを浸透させ、会社の変革を視える化するブランディングです。ブランドのガバナンス、パーソナリティ、教育の仕組みなどを一気に作りました。広告やクリエイティブなどに限らず、事業そのもの、店舗やオフィスなどの場所、また従業員の行動など、ステークホルダーにとっての全ての体験がブランドを作ります。この4つにパーパスを植え付けて従業員の行動変革を起こし、それがブランドを創っていく。社内から「業務にどうブランドを持ち込めばよいか」と相談を受けるようになりました。
坂本:「広報の仕事とは何か」という問いに対して、「ステークホルダーの視点を経営の力に変えていく仕事」と答えています。私たちの一番の武器はステークホルダーの視点を知っていることで、それが経営の意思決定や実行のクオリティを上げることにつながると考えます。以前の所属企業で、経営改革に対し社員が疑問を持ったり一部に反発があったりしたことがありました。そこでオンラインで、経営トップに忖度なしに質問できる対話の場を設けたところ、率直な質問が次々に出て、社員の理解を深める場となりました。経営者にとっても社員の視点を理解することができ、それが次のステップに生かされる建設的な対話を進めることができました。この「経営とのダイアログ」機会はのちに株主にも広げました。ちなみに、「心理的安全性」という言葉は社員についてよく使われますが、経営陣にとっても対話しやすい環境を整えることは重要です。日々マーケットや社員の視線にさらされ、常に緊張状態にありますから。
相川:経営陣との距離感は会社によって違いますが、悩まれるところではないでしょうか。定期的に会話できる場を設定するのも重要ですし、たとえば経営会議を傍聴させてもらうのも一案かと。現状の経営が世間的にどう見えるか把握するには、議事録だけでは難しいですから。また、何か起きた時こそ経営との距離を縮めるチャンスになりうると思います。会社のレピュテーションについて、経営の執行側が社外取締役から指摘を受ける時などですね。一方、攻めの広報という点では、ストレートニュースのメディア掲載にとどまらず、会社の戦略や理念を理解していただけるような発信と考えています。それをオウンドでもSNSでも語っている。端的に言いますと、経営サイクルとリンクした発信が自分たちの施策で常態化できているかということだと思っています。
最後に一言
相川:コーポレートコミュニケーションは経営機能のひとつです。経営をドライブしていく役割を皆さまと一緒に担い、よりよい社会を作っていきたいと思っています。同志としてよろしくお願いします。
坂本:最近あらためてPRSJ宣言を読んで、めちゃくちゃよいと思いました。主語を「広報」と読みかえて共有します。「広報(日本パブリックリレーションズ協会)は/倫理観と信頼感に基づいた創造的な対話づくりの力で、/人々の中に共感を生み出し/世界を変えるソーシャルイノベーションに/寄与していきます。」対話はゴールではなく、ソーシャルイノベーション。新しいものを生み出す広報でありたいと思っています。
飾森:金融はあらゆる業種のお客様と接点があるので、最近、営業のもちかけによって、企業のお客様との対話の機会がたくさんあり、うれしく思います。企業やカルチャーを変革することや、一緒に社会を良くしていくことについてお話ししています。これは金融という中立的な立場だから可能なのかもしれませんが、対話をつくっていくのがPRプロフェッショナルに求められることなのではないかと。自分自身も途上ですし、これからも皆さんと一緒に取り組んでいけたらと考えています。
<開催概要>
セミナーの詳細はこちらをご覧ください
https://prsj.or.jp/event/management2024/
日本パブリックリレーションズ協会(PRSJ)では、今後も会員の皆さまに有益な情報提供や活動の様子をお知らせして参ります。
文責:塚田 真己(広報委員会)