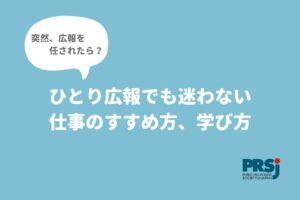株式会社博報堂
シニアPRディレクター
遠藤祐氏
PRの世界に足を踏み入れた頃、マスメディアは社会の公器として、絶対的な存在感を放っていた記憶があります。新聞を読み、テレビを見ることで、社会の「共通の話題」や「大きな物語」が形成されていた時代でした。
インターネットとSNSの爆発的な普及は、その様相を一変させました。かつて現場で共に汗を流した同年代、あるいはそれより若い世代が、メディアの要職に就く機会も増えました。それとともに、私たち広報・PRに携わる者もまた、時代の大きな転換点の中にいることを痛感させられます。
世論は無数のチャネルによって細分化され、時に先鋭化し、人々は自らの信条に合った情報だけが届くフィルターバブルの中で、エコーチェンバーとなり、異なる意見に触れる機会を失いつつあるのではないでしょうか。
この傾向は、特に米国で顕著です。社会の分断はメディアの分断とも深く結びつき、メディアは客観的な報道機関としてではなく、より明確に「左派」「右派」といったラベリングもされるようになりました。日本においても、特定のイシューに対する社会の反応は、時に過剰なまでに感情的になり、建設的な対話を困難にしてきているように感じます。
先日、あるメディア関係者との会話で、深く考えさせられる話がありました。記者の評価において「エンゲージメント」、つまり、いかに多くの読者に読まれ、反応を得られたかが重要な指標になるというのです。極論すれば、「読まれない記事」の価値は低くなってきつつあるということかもしれません。
ビジネスとしてメディアを考えれば、それは合理的な判断なのかもしれません。しかし、この流れを無条件に受け入れてよいのでしょうか。世間の耳目を集めやすい刺激的な見出しや、対立を煽るような論調ばかりが溢れ、社会にとって重要であっても、地味で複雑な問題が報じられなくなるとしたら、それは、「知る権利」を徐々に痩せ細らせ、健全な世論形成を阻害することに繋がりかねません。
この問いは、PRパーソンにも突きつけられています。自社やクライアントの利益のために、エンゲージメントが高まる手法にばかり頼ってはいないか、短期的な話題作りを優先するあまり、社会との長期的な信頼関係を損なうようなコミュニケーションに加担してはいないか。
絶対的な羅針盤が存在しない時代だからこそ、自らの中に基準を持ち、それを守っていかなければならないでしょう。異なる意見を持つ人々との間に橋を架け、建設的な対話を生み出すこと、それがパブリックリレーションズの専門家である私たちの仕事とも言えるのではないでしょうか。
教育委員会では、こうした時代の要請に応えるべく、メディアの第一線で活躍される方々をお招きする「定例研究会」をはじめ、様々な学びの場を提供しています。
変化の激しい時代だからこそ、立ち止まり、対話し、思考を深めることで、よりよい未来を切り拓くヒントになればと思います。また、委員の皆さまには立案時にはいつもお力添えいただきまして、この場をお借りして感謝申し上げます。
会員の皆さまにも積極的にご参加いただき、違う観点を吸収しながら、今の時代のPRパーソンのあるべき姿を一緒に模索していければと思います。引き続き宜しくお願い申し上げます。